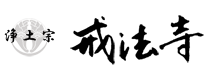住職の言葉
「今月の言葉」や「法話」一覧ページです。
住職:長谷川岱潤
住職の言葉 - 一覧
2023年11月1日 - ≪今月の言葉≫
少年の瞳して阿修羅のしぐれをる 鍵和田釉子
急な寒さに震えてしまう今日この頃
様々な現実は、もの悲しげな瞳にしかならない。
絶望の明日しか見えない現実を生きるには、
もはや念仏しか力にならない。
2023年10月1日 - ≪法話≫
10月のお話
ホームぺージをご覧いただきましてありがとうございます。今月は弟子の岱忠が担当させていただきます。
暑さ寒さも彼岸までとはよく申したもので、朝夕は涼しくなってきました。まだまだ暑い日もありますが、徐々に涼しく過ごしやすい季節になってきたように感じます。
さて、10月に入りますと、胸に赤い羽根をつけた人をあちらこちらで、よく見かけるようになります。私も、ボーイスカウト活動をしていた時、早朝から子供たちと一緒に駅前で赤い羽根の活動を行っていたことを思い出します。この赤い羽根の運動は、赤い羽根や共同募金と略されたりしますが、正式には赤い羽根共同募金といわれ、1947年に始まり、現在に至るまで76年の歴史を持ちます。私たちひとりひとりがお金を出し合い、実際に困っている方々に少しでも生活の足しになればという、助け合いの運動です。
私たち世代ですと、金八先生のお説教で「人という字はお互いに支え合ってヒトとなる」という名セリフを思い出す人も多いかと思います。もちろんその通りで、私たち人間は、一人では生きていけないもので、助け合って、支え合ってはじめて人としての営みができるのだと思います。ただ、悲しいことに、助け合い、支え合うのも人、いがみ合い、奪い合うのも人の行動なのだと思います。どうしても、自分中心に考えてしまい、相手を思いやる気持ちが欠けてしまいがちです。
私自身が子供のころは、募金箱を肩に下げ、駅前で声を張り上げて「赤い羽根にご協力お願いします!」と叫んでいましたが、成人し指導者という立場になり、子供たちに赤い羽根の共同募金の説明をすることが増えました。その時は、「ひとりひとりは少ないお金でも、みんなで少しずつ出し合えば実際に困っている人を少しでも助けることができる、そんなおもいやりの心を形にしたのが赤い羽根のバッチだよ」と説明していました。
何かを成すときに、それが形として戻ってくるということはとても充実し大切なことなのかもしれません。そして、今、僧侶となりもう一歩先に思うことができました。
それは、どうしてもその羽が欲しい、募金をすれば誰かを助けているという実感や達成感が欲しいという対価を求めるのではないということなのではないでしょうか。もちろん形にしていくということも大事なことの一つではありますが、形には欲が付き物で、募金額の数字に目を奪われてしまい、また、これだけやったんだからという思いになってしまいます。
それよりも、助け合い、支え合うという言葉が出ないほど当たり前のような平等な世界になることが必要なのだとは思います。ですが、悲しいことに常にその思いが続くわけでもなく、又、人間にとっては限界があります。どうしても、平等にすべての人の幸せを願い、行動することができないのが私たち人間なのだと思います。
このような断片的な限界のある人間の慈悲よりも、すべてを等しく、平等にお救いくださると誓い仏さまになられた阿弥陀さまの人間とは明らかに違う次元の慈悲に帰依し、我が名を呼べば必ずや西方極楽浄土に往生させるという「称名念仏」のみ教えを実践していくことなのだと思います。
合 掌
2023年10月1日 - ≪今月の言葉≫
秋深き 隣は何を する人ぞ 松尾芭蕉
この句は晩年の病床に臥せていた時に詠まれました。
厳しい暑さが過ぎ去り、みのりのある秋。
隣人の灯りを怪しむのではなく、
思い馳せる気持ちが、心豊かにしてくれる気がします。
2023年9月1日 - ≪法話≫
9月のお話
ホームページをご覧いただきありがとうございます。先月中旬から椎間板ヘルニアを患ってしまい、起き上がることすらもかなわずご迷惑をおかけしました。レントゲンとMRIによる検査で治療方針を決めまして、リハビリをしながら腰の痛みとにらめっこという状況ですが、着実に一歩一歩快方に向かっていると思います。
9月1日は「防災の日」です。この日は、10万5千人以上の方々が死者・行方不明者となる関東大震災がおきた日ですが、7月下旬の日本赤十字社のアンケート調査でその由来を知らない人が49.2%と約半数にのぼるというデータが公表されました。今年は1923年の関東大震災から100年目をむかえ、その大震災の教訓や、二百十日と言われるように立春から210日目の9月1日が台風の襲来する時期とされ警戒する言葉もつくられ、災害の備えを怠らないようにとの戒めもこめられています。
近年では、8月にも大型台風が襲来し、また、線状降水帯という言葉を耳にする機会が増えたように、台風が通過する地域以外でも災害級の被害が増加しています。気候の変動も含め、防災の意識が強いものだと思いましたが、データにしてみるとそうでもないように感じます。大地震の備えだけにとどまらず、過去に類をみないような地域での河川の氾濫や、もはや災害ともいえる猛暑が続く昨今、防災の日を機会にもう一度見直してみたいと思います。
そして、忘れてはいけないことがあります。それは、関東大震災の時に起きた悲劇です。甚大な被害をもたらした、関東大震災での混乱の中、デマ情報が流れ、朝鮮人や中国人にたいして大虐殺をおこなったということを忘れることはできません。「井戸に毒をいれた」や「暴徒となって襲ってくる」など様々なデマ情報が流れ、「自分たちは正義だ」というような偏った感覚を持ち正当性を主張し人の命を奪ったのです。どこに人の命を奪うことに正当性があるのでしょうか。ましてや、等しく震災による被害を受け、助け合わなければならないような状況であるのにも関わらず。
このように考えますと、防災の意識で何よりも大切なことは、災害が起きてしまった時による被害を拡大させてしまう「人災」を防ぐことなのだと思います。悲しいことに、災害を絶対に防ぐということはできないのかもしれませんが、被害を拡大させない為にも、起きてしまった時、そしてその後の行動と心構えが大切なのだと思います。私自身も「心構え」が大切だと分かっていても、その場に居合わせたとき平常心をもって対応できるかわかりません。ですが、実際に自身が経験していないことであっても、先人の方々からの教訓を学び、一つでも多くの教訓を次につなげられるよう行動したいと思います。自分だけが助かりたい、自分たちだけが助かりたいという行動から他者を虐げてはならないと肝に命じたいと思います。
自分には関係のないことと切り捨てるのではなく、物事ひとつひとつは自身に関係しているということを自覚し、その学びから次の行動に移せていければと思います。人を排除する行動よりも人を思いやる行動こそが尊いことなのだと思います。
合 掌
2023年9月1日 - ≪今月の言葉≫
大いなる ものが過ぎ行く 野分かな 高浜虚子
大自然の人知を超えた台風(野分)を目の当たりにした、
昭和九年9月21日の室戸台風が上陸した日に詠まれた句です。
古今東西、悲しいことに災害は起こります。
誰かを押しのけるのではなく、手を取り合って生きることが、
人間の美しさなのだと思います。
2023年8月1日 - ≪法話≫
戒法寺ホームページをご覧頂きありがとうございます。
副住職が椎間板ヘルニアになり、永く座ることもできないほどの痛さとのこと、現代の治療はとにかく1ヶ月間絶対安静がいいということで、この原稿は九月と交代することになった。今無理して九月に動けなくなるのと、今安静にして九月は動ける可能性があるのだったらどちらがいいですかと言われてしまえば、九月のお彼岸に備えてもらうしかない。痛みは本人にしかわからないもので、気のどくだとは思うが、なんとも同情するのが難しい病だ。
さてこの暑さ、炎天下にいると必ず思い出す話がある。道元禅師の『典座教訓』の中にある中国での修行中の話だ。炎天下で椎茸を干している老僧がいたので、道元さんが歳を聞くと六十八歳と言う。そこで、そのような仕事もっと若い人にしてもらったらと言うと、「他は是れ我にあらず」他人は私ではないと言う。そこで「日が陰ってからしたら」と言うと、「更に何れの時をか待たん」あとでと言っていて、そのときが来るか。と言われもう何も言えなかったという話です。
「今、ここで、わたしが」なすべき仕事をしっかりとせよ。
いかにも禅宗ぽい教えです。現在六十九歳直前の私は、昔は大変な老僧と思われたのだなあと、別の感慨を持ってしまいましたが、まだまだ若い部類に入る現代の僧侶の世界では、暑さくらい頑張らなくてはと身を引き締める話です。
中国の古典『淮南子』に「塞翁が馬」という話があります。老人の飼っていた馬が逃げ出して、北の胡の国に行ってしまいます。近所の人は「お気の毒に」と言いますが、老人は「なあに、これはいいことですよ。きっと」と言うのです。しばらくしてその馬が駿馬を連れて帰ってくるのです。近所の人は「よかったですね」と言うと老人は、「いやいやこれは悪いことですよ。多分」と言います。すると老人の息子がこの駿馬から落馬して足の骨を折る重傷を負います。また「お気の毒に・・・」と言うと、「なあに、これはきっといいことですよ」と返します。そして案の定、胡の国と戦争になり、若者がみんな出兵し、八割から九割が戦死してしまいますが、息子は無事でした。足が悪いのでかり出されずにすんだからです。ここから「人間万事塞翁が馬」という言葉が生まれたようです。この人間はじんかんと読んで、世間の意味です。
でもこの話多くの人が、「苦は楽の種、楽は苦の種」のように、苦と楽が交互に来ると理解いしているようですが、苦の中にも楽があり、楽の中にも苦があると読むべきだそうです。苦を苦として見つめたとき、他のものが見えてくるということです。
合 掌