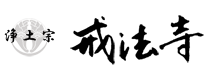住職の言葉
「今月の言葉」や「法話」一覧ページです。
住職:長谷川岱潤
住職の言葉 - 一覧
2025年7月1日 - ≪法話≫
7月のお話
ホームページをご覧頂きありがとうございます。今月は弟子の岱忠が担当させて頂きます。
昨年は、気象観測史上最も短い梅雨が終わり酷暑となりましたが、今年も六月中旬から35度超えをする地域もあり、近年のこの時期から猛暑となっているようです。線状降水帯のような身の危険さえ起こりうる気候変動もあるかとおもいます。どうぞお体を第一にご自愛くださいませ。
今月の6日は三祖良忠上人の御命日でございます。三祖とは、元祖法然上人、二祖聖光上人、三祖良忠上人の良忠上人を指します。
三祖良忠上人は、正治元年(1199)島根県那賀郡三隅町で誕生されまして、現在ではその邸跡に良忠寺があります。
十一歳で『往生要集』の講説を傍聴し、十六歳で出家しました。十八歳の折に、『大聖竹林寺記』を閲覧し、この生涯で悟りを得る教え「聖道門」から、この生涯でお念仏を申し阿弥陀仏に極楽浄土へ救って頂く教え「浄土門」へと転換され、日々お念仏をお称えするようになりました。
三十八歳の時、平家琵琶の開祖とされる生仏法師の勧めにより、久留米善導寺におられました二祖聖光上人と対面し、浄土宗の伝灯を余すところなく受け継がれました。
二祖聖光上人は「然阿(良忠上人)は予が若くなれるなり。宗義に不審あらば然阿について決せよ」と門弟一同に告げるほど厚い信頼をよせ、良忠上人は浄土宗の神髄『末代念仏授手印』を理解したという、『領解末代念仏授手印』を書き示し聖光上人は良忠上人こそが、正しい後継者であると認可されました。
以来、千葉や鎌倉を拠点として関東の布教に勤められ、二祖聖光上人の西国布教とあいまって、浄土宗が全国に広く行きわたることに大変な貢献をされました。
三祖良忠上人のお言葉に
五濁(ごじょく)の憂世(うきよ)に生まれしは
恨みかたがた多けれど 念仏往生と聞くときは
かえりてうれしくなりにけり
と歌われ、私は濁れに濁れたこの憂いの世に生まれ、それを恨む心が起こることもありますが、この人間の世に生まれたからこそ、極楽往生へと導かれる念仏のみ教えを聞くことができたのですから、かえって嬉しく思うのです。
まさに今、戦争や天災などの時代の汚れ(劫濁)、誤った考え方による濁れ(見濁)、人間の心の中にある煩悩による濁れ(煩悩濁)、社会全体の心の濁れ(衆生濁)、自他の生命が軽んじられる汚れ(命濁)このような五濁の世に、お念仏の御教えにめぐり逢えた喜びと共に、これを伝え広める礎を築き上げた良忠上人に感謝の思いをこめ、ますますのお念仏の生活に私自身励んでまいりたいと思います。
また、私が浄土宗僧侶となるために修行道場二期目で多くを学ばせて頂いた、鎌倉の良忠上人開山大本山光明寺、あらためて良忠上人を偲んでお念仏をしたいと思います。
合 掌
2025年6月1日 - ≪今月の言葉≫
腹悪しき僧こぼしゆく施米哉 蕪 村
毎年六月に京都の山で修行する僧に、
朝廷が米と塩を施す「施米」が行われていた。
怒っている僧はぶつぶつ言いながら
せっかくの米をこぼしながら去ってゆくという。
2025年6月1日 - ≪法話≫
6月のお話
先月中旬「世界で最も貧しい大統領」と呼ばれた、ウルグアイの元大統領ホセ・ムヒカ氏が亡くなった。89歳でした。彼は以前「私は質素なだけで、貧しくはない」とおっしゃり、2012年の国連演説でも「貧乏とは少ししか待っていないことではなく、無限に欲があり、いくらあっても満足しないことである」と言っています。この言葉は、まさに仏教の教える「餓鬼」の定義です。
仏教の論書の中に、「餓鬼」とは三種あり、一つは無財餓鬼、いわゆる何も所有していない、そのものずばりの餓鬼です。二つ目は少財餓鬼、少しは持っているが、到底満足できない見るからに餓鬼です。そして三つ目は多財餓鬼、充分に待っているが、満足できず、際限のない欲望の餓鬼です。「餓鬼」つまり欲望とは状態ではなく、そのものの心をさします。河上肇の『貧乏物語』の中に「人は水にかわいても死ぬが、おぼれても死ぬものである」というセリフがあるそうですが、貧しさを論ずることは、同時に豊かさを論じることであることを語っています。
ムヒカ氏は生前、「私たちは経済発展するために、この地球にやってきたわけではありません。」と語っていました。私たちに生きることの意味や、幸せとは何かを示してくれた方でした。
少し前の話ですが、ある方が同じカップラーメンのCMを日本と韓国で見て、その違いに愕然とされていました。日本では兄弟が取り合いをして、「こんなにおいしいカップラーメン」と言っていたのに、韓国では兄弟が譲りあいをして「こんなにおいしいカップラーメン」としていたのです。この話を聞いて「負けた」と思ってしまうは私だけでしょうか。
戦後80年、世界の極貧国としてスタートした韓国が、今や日本にも近づく経済大国になっています。それでいてこの日本人との感性の違いはどうしてなのでしょうか?最近のニュースを聴きながらも、何か日本人が変わってしまったような気がしてしまうのは私だけでしょうか?
昔、ひろさちや氏が何度もしてくれた話に、一つのケーキを兄弟で二つに分けて食べる話があります。兄がもらってきたケーキを母親が弟と二つに分けて食べなさいと言い、お父さんが二つに分けて食べる理由を兄弟に問います。兄は弟がかわいそうだからと言い、弟は今度僕がもらってきたら半分あげるからと言います。 お父さんはその両方とも違うと言います。かわいそうでは、けんかしていたらあげなくなり、お返しを期待しているのでは仏教の布施の心ではなくなります。お父さんの気持ちは、二人で食べたほうがケーキがおいしいと思える子になってもらいたいからだと言う話です。そしてこの心が布施の心だと言っています。
合 掌
2025年5月1日 - ≪法話≫
5月のお話
ホームぺージをご覧いただきましてありがとうございます。今月は弟子の岱忠が担当させていただきます。
朝夕の気温は低く、日中は暑い日差しがあり、寒暖差の激しい初夏となりました。服装選びも難しく体調を崩しやすい気候となりますが、無理せずどうぞご自愛くださいませ。
さて、今月のゴールデンウィークは飛び石のような形となり、なかなか長期休暇がとりずらい日程となっていますが、この連休の中の5月3日「憲法記念日」に注目してみたいと思います。
日本国憲法は、ご存知の方も多いとは思いますが、昭和22年5月3日に施行され、「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」を柱として私たちとその子供たち、子孫のために平和を念願し、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓うという素晴らしい憲法として成立し、世界的にも高い評価を受けています。近年、改憲・護憲など様々な議論が起きておりますが、この崇高な平和主義を掲げるのであれば、お互いがお互いを尊重しどちらか一方の正義を主張し、強いるのではなく、平和を基に認め合い歩んでいくことを忘れてはいけないのだと思います。
仏教には「戒」と「律」というものがあります。お釈迦さまのもとで、僧侶が大勢集まり生活を共にするようになると、秩序を維持するための規範が必要となり、この「戒律」ができたのです。集団におけるルールとして「律」があり、これを破る場合罰則が与えられます。一方「戒」とは自ら積極的に守っていこうとする、言わば努力する決めごとです。仏教徒の大原則として、戒・定・慧の三学を修しさとりを目指すことが根底にあります。煩悩をおさえ心を戒め、それによって心を静め、そして静かになった心で真理を知るという、戒律から始まる非常に重要なプロセスなのです。
ですが、この三学を修めるということは非常に難しく「智慧第一の法然房」と呼ばれる法然上人は、僧侶であるにもかかわらず「我れ三学の器にあらず」として、三学の実践とは別に、誰もができる「南無阿弥陀仏」と称える、称名念仏の教えを説きました。
法然上人は、「酒を飲んではいけないのでは」という質問に「飲むべくもなけれども、—この世の習い」と答えられています。だれもが称えることのできる念仏を称えることが第一であり、日常の些細なことよりも本質的なことが大切なのだと示されているのだと思います。
法律に明言されている言葉や条文があるから、それを守るというのではなく、根本は人々が共に幸せに歩んでいけるようにするための究極の原則が憲法なのだと思います。そして、すべての人が共に歩み平和になるには、自身が煩悩に満ちて、正しくみることができず固執してしまうことを知ることが必要なのだと思います。まさに私たち自身が「三学の器にあらず」と言えることなのだと思います。
誰もが凡夫であるということを自覚するからこそお互いが歩みより、その心がお念仏の御教えには内包されているのだと思います。
まずは、私自身、傲慢にならないようお念仏を称え続けたいと思います。
合 掌
2025年4月1日 - ≪今月の言葉≫
まさをなる空よりしだれざくらかな 富安風生
寒暖差の激しい三月が終わり、
ようやく控えめな四月がやってきました
稲穂同様枝垂桜に見習って
生きてゆきましょう
2025年4月1日 - ≪法話≫
4月のお話
寺の門前の三月の掲示板に「すぐに役に立つことは すぐに役に立たなくなります」という灘高校の以前の校訓を書いたところ、お檀家さんから「私は”後でと”言われることが一番嫌いで、すぐにやってくれないと頭に来る方なのですが、やっぱり駄目ですかね」と言われ、「いやいや、あなたの気持ちに私も同感ですが、あの言葉はそういう意味ではなく、受験高校として名高い灘高校として、いわゆる詰め込み式の受験勉強は駄目ですよという意味だと思いますよ」とお答えしました。
昔「手間を省くと、手間が増える」という言葉に苦笑いしたことを思い出し、灘高校のこんな言葉を書いてしまいました。現代社会の目標が、「早くて、便利で、快適の追求」と信じ込んで進んできた我々ですが、人間が幸せになることって、本当にそれでよかったのかなと、少し疑問に感じ始めています。
最近大学の先生と話をすることが多いのですが、最近の学生のレポートにみんな頭を悩ましていました。何人もの学生が内容は完ぺきなのですが、全く同じような文章のものを送ってくるそうです。確信は持てなくてもこれは生成AIを使ってるなと推測して落第点ぎりぎりの評価にし、苦情があれば申し出てくださいと言っても、誰も出てこなかったそうです。
楽しく生きることが人生最高の価値としている人が多いようですが、確かに楽という字は「らく」とも読めますから、たのしいとらくするは今や同義語になっているのかもしれません。しかし本来は全く違う意味です。らくして楽しければ最高だと言うかもしれませんが、らくして楽しいのはその場限りの、あまりに刹那的と思ってしまいます。感動が続く喜びは味わえないのではないでしょうか。仏教ではそうした楽しみを「欲」として、断ぜよと言います。その欲は決して満足することがないからです。
インドの昔話で、牛を99頭飼っている裕福な人がいました。彼はあと1頭で100頭になると思うと、ふるさとに牛を1頭飼っている友人を思い出し、ぼろぼろの服に着替え、その男のもとを訪ねます。「いいなおまえは、俺はもう生きてゆけないよ」と言うと、友人は「悪かった何も知らないで、牛が1頭いるからこれを連れてゆけ」と言って牛を差し出します。金持ちの男は牛を連れ帰り大喜びで寝たという話です。この後この話は「どちらの男が幸せでしょう?」で終わっています。どう思いますか?
金持ちの男は翌朝きっとこう言うでしょう。「次は200頭だ」。
一方牛を差し出した男は、友人の手助けができたことで、ずっと心晴れやかに暮らすでしょう。これが仏教のいうところの幸せだとしています。2000年前のこの話を、今我々はどのように味わうか、今それが問われているように感じます。
合 掌