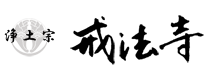住職の言葉
「今月の言葉」や「法話」一覧ページです。
住職:長谷川岱潤
住職の言葉 - 一覧
2022年5月1日 - ≪法話≫
5月のお話
今の日本は世間の雰囲気がおかしくなっています。東大で反戦を訴えた講師が、学校側やネットで批難の対象になったり、ロシアや中国のことを少しでも認めるような言動をすると、大変なことになってしまいます。ロシアの侵略を肯定する気は全くないのですが、かといってウクライナの流すニュースをそのまま信じることも、戦時中の日本と一緒で、正しいとは思いません。戦争に良い戦争などあるわけがありませんから、一方の情報だけを信じ、武器の給与をするナトー、とりわけアメリカを誰も問題視しないことに、疑問を感じるのはおかしいのでしょうか。
とにかく戦いを終わらせること、武力を用いない問題解決、それが憲法九条を持つ日本の説くべき姿勢だと思うですが・・・。
こんなことを言えば、それは理想論だと笑われてしまうでしょう。しかし問題解決に当たる心の持ちようを、西洋では子どもの純真無垢な心を理想としました。キリスト教では「幼な子のようにあれ」と言いました。しかし仏教では子どもの純真さは時に残酷さもあることから、邪念を克服した無心を理想としています。無心はうつろな心ではありません、こだわりのない心です。鈴木大拙師はこんな話を紹介しています。
きこりが山で木を刈っているときに、サトリという動物と遭遇しました。とても珍しい動物なので、きこりは捕らえてやろうと考えました。「お前は俺を捕まえようと思っているな」サトリは人間の心を読むことができるのです。ぎょっとしたきこりにサトリは続けて「お前は言い当てられてびっくりしているな」、そして「今度は俺を殺す気だな」、少し時間をおき「おやもう捕まえることも諦めたか」。その言われたのち、きこりは本当にサトリのことを忘れてしまいました。そしてただ木を刈っていた。その時、きこりの打ち下ろした斧の先が取れ、飛んでいってしまったのです。そしてその斧の先がサトリに命中してしまいました。サトリは人の心は読めても、無心は読めなかったのです。そんなお話です。
私たちは良い仕事をしよう、人から褒められようと、あれこれ考えています。そんなこだわりがあるとなかなか良い仕事ができないでいます。良い仕事はこだわりがなくなったときにあんがいできるものです。無心とは、こだわりのないあっけらかんとした心だというのです。
さて、無心で問題解決に当たるとはどういうことでしょうか。それは心の中の理想論をしっかり持ちながら、問題解決に当たることを指すことのように思います。今政治家が守らなくてはならないものは、領土保全でも政権維持でもなく、国民の命です。つまり戦いが終わること、それ以外ないと思うのですが。
合 掌
2022年4月1日 - ≪法話≫
3月の春彼岸中日法要の様子・4月のお話
4月のお話
寺にある一本の桜も満開を過ぎ、見る見るまに足下の地面を花びらの絨毯に変えています。梅と違い、桜は一気に満開になり、一気に散ってしまう。むしろ散る見事さが人々の心に強く印象づけられる花で、軍歌にも「咲いた花なら、散るのは覚悟」と歌われ、特攻隊の部隊名にも山桜隊や若桜隊などと使われ、特攻機に桜が描かれるなど、桜は勇ましさの象徴でした。死を美化するときに使われてきた事が多いのかもしれません。
ウクライナの戦争の報に接し、ウクライナの大統領の言葉を聞きながら、二十世紀の戦争の時代と何一つ変わらない、国民は命をかけて国を守ると豪語する政治家の言葉にうんざりしてしまいます。 「戦況」と言う言葉の裏で、多くの人が亡くなっていることを思うと、なんとしてでも、何を犠牲にしても戦争を止めること、何よりも優先すべきは人の命であるはずだと思うのです。
日本もこの優先順位を間違ってしまっているように思います。生産コスト、人件費の安い国で全て生産してきたことにより、二年前はマスクさえなくなってしまいました。今は半導体など支障を来しているようです。でも最も怖いのは食料です。日本の食糧自給率の低さは、ウクライナの戦争でさえ、影響をもたらしています。
私たち人間の価値観はどうでしょう。ひろさちや氏が以前こんな話を教えてくれました。あの「うさぎとカメ」の話をインドでしたところ、誰もが「この話はカメのような人になってはいけないという話ですね」と言うそうです。そこで「いやいや、日本ではこの話は自分の力にうぬぼれて怠けたうさぎはだめで、一生懸命努力すればうさぎにも勝てるカメが偉いという話です」と言うと、インドの人は「それは違う、一緒に競争している相手が途中で寝ていたら、起こしてあげるのが当たり前だ、もしかしたら具合が悪いのかもしれないじゃないか」というのです。これには目から鱗でした。私たちは努力することの尊さばかりが頭にあり、人として生きる意味、人の道を忘れていたのです。人のことを思いやる心、仏教が一番大事にしている慈悲の心を忘れていたのかもしれません。これでは阿難尊者が餓鬼になるぞと脅されたように、私たちはすでに完全な餓鬼になっているのかもしれません。カメでもかけっこの競争でうさぎにも勝たなければだめだと教えられた私たちは、勝った人はえらく、負けた人は怠けていたんだとののしってきたのかもしれません。もうそんな価値観やめましょう。努力がしたくてもできない環境の人もいます。はじめから持っている能力の違う人が、そもそも競争をすること事態が馬鹿げているのです。みんなそれぞれが持っている能力で尊いのです。人と比べることではありません。それがお釈迦様の誕生の偈「天上天下唯我独尊」の意味です。
合 掌
2022年4月1日 - ≪今月の言葉≫
さまざまなこと思ひ出す桜かな 芭 蕉
今年も三ヶ月が過ぎ、桜も盛りを超えた。
コロナはまだまだ収束の兆しはなく、
ウクライナの戦争も悲惨を極めている。
何か光はないか、せめて熱を感じるものをさがしたい。
2022年3月1日 - ≪今月の言葉≫
人界のともしび赤き彼岸かな 相馬遷子
人界とは彼岸ではなく此岸、この世のこと
ともしびを灯す本堂の荘厳の中で、仏さまと相い対す
そんな一時を作ってみませんか
心の声が聞こえてくるかもしれません。
2022年3月1日 - ≪法話≫
3月のお話
2月の末から急に暖かさを感じる季節になりました。その前の厳しさを思うと、まさに「冬極まりて、春近し」の言葉通りですね。
また新型コロナのオミクロン株の変容で、感染は収束してくれるのかわからなくなってしまいました。いつまでこんな状況が続くのか不安が募るばかりです。
今ヨーロッパではロシアのウクライナへの進攻が始まって大変な戦争状態になっています。「戦争は最大の人権侵害だ」と言ったのは解放の父松本治一郎氏ですが、全くその通りで、たとえどんな利用があろうと戦争だけはしてはいけないことだと、様々な惨状を聞きながら痛切に感じます。結局一番の被害を被るのは一般の市民であり、一番弱い立場の人々であることが多いのです。
さて、今年は日本の人権宣言とも言われる水平社宣言ができてちょうど百年になります。これは部落差別に対して当時の政府がごまかしの融和政策しかしてこなかったことに、抗議して結成された水平社の結成大会で発表された宣言書です。この宣言書を書いた人西光万吉氏は浄土真宗の僧侶で、画家であり劇作家でもある彼は、情熱を持って書き上げました。「全国に散在する吾が特殊部落民よ団結せよ」で始まり「吾々がエタである事を誇り得る時が来たのだ ・・・水平社はかくして生まれた 人の世に熱あれ 人間に光りあれ」で終わるこの宣言は、今ではとても書けない差別語と過激な言葉に満ちていますが、人間は同情されて生きるのではなく、それぞれが尊厳を持っていることを確認し、人間としての誇りをもって生きるということを宣言した、まさに人権宣言です。「吾々はいたわられるものではない」とし、いたわる行為は相手の発言を封じ込める行為だとしているのです。これが今から百年前、大正11年に書かれていることに、そして世界人権宣言ができる26年も前にできていることに驚きさえ覚えます。
しかし水平社はその後戦争に突入する社会の流れの中で、戦争に協力し組織は解散します。戦後改めて戦争に反対することをもって生まれたのが現在の解放運動と言えるでしょう。戦争が始まるときその中にいると誰もが自己を失いわからなくなります。仏教界もその当時進んで戦争に協力していました。この度のロシアでさえ、平和維持のためとしてウクライナに侵攻しています。アメリカは昔戦争を終わらせるためだとして原爆を投下しました。
戦争だけはいかなる理由があろうとも認めることは絶対にしてはいけないことだということを,今こそ強く思う必要があるでしょう。
合 掌
2022年2月1日 - ≪法話≫
2月のお話
寒さ厳しい今年の冬、ようやく立春を迎えますが、本当の寒さはこれからかもしれません。何年か前の冬、大寒が一番温かく、立春が一番寒かった年もありました。
また新型コロナのオミクロン株への変容で、感染者の数は一気に倍増し、どこまで行くのか不安が募るばかりです。感染しないまでも、ここまで感染者が増えると、濃厚接触者となる可能性は高くなり、活動制限がかかってしまうことになりかねません。注意、予防しきれないこともあり、仏さまに頼るばかりです。
さて、最近近所にできた新築の家の表札が、住所だけで名前がありませんでした。マンションなどでは表札すら出さない家がほとんどのようですが、一軒家でもそうなったのかと少し驚きでした。
表札に名前を出さない理由は、以前は出すことによって何らかの差別に会うからと言われていました。つまり、有名人であったり、アジア系外国人であったり、刑を終えた人であったりしたことがわかってしまうから、会えて出さないという人がいたわけですが、最近は少し違うようです。名前を出さない、匿名を求める人がどんどん増えているという話をよく聞くようになりました。
つい先日の『天声人語』で、「いわれなき中傷やトラブルから身を隠そうと、匿名を求める人が増えているのだろう、ただ、名乗らぬ人々の世界は魔物にも居心地が良さそうだ。名前とは、それを呼ぶ他者の存在を前提とした社会の産物。匿名の広がりには、寂しさとともに危うさを感じずにはいられない。」という文を見つけ、同感しました。あまりにも情報が広く、多く、拡散して伝わる中で、相手とのコミュニケーションが、その密度をどんどん軽薄なものにし、相手を傷つけることに、何も躊躇しない人々が多く現れ、密度の濃いコミュニケーションがなされなくなっている現代の象徴が、名前が消えて行く現象なのかもしれません。
昨年のお寺の掲示板大賞の入賞句の中に「もっとも優しい言葉は、その人の名前を呼ぶこと」というのがありました。しっかり相手を特定し、今私が話したい人、今私が必要な人はあなたですと言う言葉が、まさに相手の名前を呼ぶ行為なのではないでしょうか。『天声人語』の最後は、「誰にとっても大切な名前、私が私であるための名前、それを伝えることの重みをかみしめる。」でした。
私たち浄土宗の僧侶が最も大事にしている「お念仏、南無阿弥陀仏」とは、阿弥陀様のお名前を唱えることです。南無とはある先生が「こんにちは、おはようございます、こんばんはであり、お願いしますであり、ありがとうございます、全てです」と言っています。
どんな状況、どんな感情の時でも、阿弥陀様の名前を呼んでみましょう。きっと力がもらえます。
合 掌