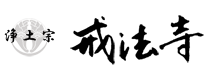住職の言葉
「今月の言葉」や「法話」一覧ページです。
住職:長谷川岱潤
住職の言葉 - 一覧
2023年8月1日 - ≪今月の言葉≫
白蓮やはじけのこりて一二片 飯田蛇笏
この暑さも、もう峠が見えてきたと思いたい今日この頃
朝花を開き、夕べに閉じるを繰り返し四日目の午後、
水面に花を散らせるという蓮の花。
散ってなお、美しさをとどめる蓮の花
2023年7月1日 - ≪法話≫
7月のお話
戒法寺ホームページをご覧頂きありがとうございます。
6月の25日の夕方、新宿駅の駅員から「山手線の車内で男が刃物を振り回している」という110番がありました。電車は新宿駅に停車し、乗客は一時パニックになり、二人の男性が救急車で搬送され、車内は警報ブザーが鳴り、山手線、中央線、総武線なども一時運転を見合わせ、約一万四千人に影響した事件がおきました。
事件の原因は、五十代の外国人の料理人の男性が、仕事が解雇になり包丁を布にくるんで手で持っていたところ寝てしまい、その包丁がコロンと床に落ち、刃先がわずかに見えたことでした。誰かが「きゃー」「逃げろ」と叫び、後方の車両にどっと押し寄せたことで、叫びもいつしか「包丁を振り回している」「火をつけた」と先日の京王線の事件のようになってしまい大変な事件になりました。
この話を聞いてすぐに、ジャータカ(お釈迦様の前世話集)の中にある「あわてウサギ」(ジャータカ475)の話を思い出しました。海にほど近い丘に住んでいた1羽のウサギが昼寝をしていたら、後ろで「ドスン」という大きな音がしました。ウサギは飛び起き「地球が壊れた」と思い込み走り出しました。それを見た仲間のウサギたちが「どうした」ときくと「地球が壊れた」というので、これは大変だとみんなで走り出しました。そして鹿が、イノシシが、サイが、トラがと、ジャングル中の動物たちが、みんなで走り出したのです。それを見たライオンの王は走っている先頭までゆき、ウサギを見つけ聞きただします。そして「おまえは地球が壊れるのを見たのか」と聞き、見ていないのなら「その場所に確認にゆこう」と、嫌がるウサギに案内させて元いたところに戻ります。そこには椰子の実が一つ落ちていたというお話です。
山手線の外国人の方は、きっと極悪人のように扱われたかもしれません。確かに包丁を鞄にも入れずに手で持っていたのは、不用心だったでしょう。でもその後どれほど怖い時間を過ごしたかを思うと気の毒な気がします。未知なる人々の集団である電車内、隣人が包丁を持っていたら、恐怖はあって当然かもしれませんが、冷静な人が近くに一人もいなかったのかと残念でなりません。
ジャータカが作られたのは今から二千年以上前ですが、その頃から人類は何も変わっていないのだということを思い知らされます。
そして現代では、情報は拡散と同時に拡大してゆくという、もっと悪くなっていることに悲しい気持ちになります。「嘘」とか「偽物」とかと言うより、「フェイク」と言うとかっこよく聞こえてしまう錯覚、人間の質がどんどん落ちているように感じるのは、私の錯覚でしょうか。
合 掌
2023年7月1日 - ≪今月の言葉≫
よい月に背き座頭の納涼かな 伊藤松宇
座頭の納涼とは一般的には死語であり、差別語です。
目の不自由な人たちが主催する追善供養の会です。
その会ではどんなにいい月も、何の力にもなりません。
そこには純粋な本当の納涼があるようです。
2023年6月3日 - ≪今月の言葉≫
明らみて 一方暗し 梅雨の空 高浜虚子
雨雲と太陽が混在す梅雨の情景を絶妙に捉えた一句ですが、
これは私たちのこころも暗示させているのではないでしょうか。
晴れやかな心の一方で、どんよりした心の葛藤。
南無阿弥陀仏と称えて、あたたかいみ光に導かれましょう。
2023年6月3日 - ≪法話≫
6月のお話
ホームページをご覧頂きありがとうございます。今月は弟子の岱忠が担当させて頂きます。
先月18日は、戒法寺の400年祭の締めくくりとなる施餓鬼大法要をお勤めできましたことを大変感謝申し上げます。5月にしては観測史上まれに見る30℃越え、翌週には15℃と、寒暖差の大きい月となりました。10℃以上の気温差となると心も身体もついていくのがしんどい月となったのではないでしょうか。
先月の暑さにより一足先に衣替えをされた方も多かったように思えます。私たち僧侶も六月一日からは夏物の法衣を身に着けます。もちろん、衣替えは季節の移り変わりに順応するために行われ、これからむかえる暑さに備えて服を新調したりクリーニングに出した綺麗な服を取り出したりと、季節の移り変わりを感じるとともに、気持ちも心機一転、新たなこころになるのではないでしょうか。
さて、この六月についていろいろと調べてみますと、実は、6月10日は 「時の記念日」だそうです。
これは、1920年に制定され、時間を尊重し生活の改善と合理化を提唱した記念日となり、古くは、600年代後半の天智天皇の時代に唐から伝承した水時計を作らせ、太鼓や鐘などを鳴らして時を知らせたのが6月10日であることからこの日に合わせ記念日とされたようです。
「時間を大切に!合理的に!」と考えてしまいますと、ついつい「ながら作業」をしてしまっているように思います。最近ではこのながら作業の代表格にスマホが挙げれると思います。腕時計の代わりや通信手段としてだけではなく、移動中の電車のなかでも手軽に利用でき様々な情報を知ることができるスマホ。これは貴重な時間を有効利用する手段になっているのでしょうか。なにやら私は時間を潰すために使ってしまっているように感じます。時間を大切にという言葉をもういちど考えて私自身の行動を振り返ってみますと、大切な時間を浪費してスマホを見ていたのではないかと思います。
時の記念日は再び戻らない時間を大切にし、時間励行を呼びかけることが主旨なのだと思いますが、この主旨を身近な私たちの行動という意味だけに留まらず、時は「いのちの移り行き」と捉えると本当の意味での時間を大切にするということが見えてくるのではないでしょうか。
それは、季節に合わせ衣替えをするように、日々刻々と移り行く自然環境の中にいる私が手元だけに目を奪われず、視野を広げ周りを見渡してみると、より有意義な時間になるのではないかと思います。
善導大師の「日中無常偈」を詠み返してみますと
人生不精進 人、生けるとき、精進ならざれば
喩若樹無根 たとへば樹の根なきがごとし
採華置日中 華を採って日中に置かんに
能得幾時鮮 よくいくばくの時か鮮やかなることを得ん
人命亦如是 人の命もまたまたかくのごとし
無常須臾間 無常 須臾(しゅゆ)の間なり
勧諸行道衆 もろもろの行道衆を勧む
勤修乃至真 勤修してすなはち真に至りたまへ
人は生きている時に精進しなければ、たとえてみるならば根のない花がいかに美しく咲いたとしても、時間がたつにしぼんでしまう。人の命も同じで、無常のほんのつかの間のもの。もろもろの行道たちに勤める。勤修して速やかに真にいたりたまえ。
間違いなく私は時間を浪費してしまっているのだと思います。今一度、時間の大切さを自覚しより一層励んでいきたいと思います。
合 掌
2023年5月1日 - ≪今月の言葉≫
小声もて遙かと話す夏花摘 岡本 眸
夏花とは夏安居の期間毎日花を仏前に供える習慣だが、
最近ではまったく聴かれなくなってしまった。
でも今でも墓前で話しかけている檀信徒の姿を見ては、
温かな心を感じ、墓守の喜びを味わっている。