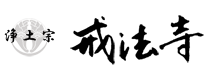住職の言葉
「今月の言葉」や「法話」一覧ページです。
住職:長谷川岱潤
住職の言葉 - 一覧
2026年2月1日 - ≪法話≫
2月のお話
今年は午年ということで、馬について調べていたら、馬は農耕でも、スポーツでも、軍隊でも昔から人間とかなり親しいし大事にされてきた動物であるにもかかわらず、なぜか言葉の中ではあまりいい意味で登場しない。”馬の耳に念仏”とか、”馬耳東風”とか、”馬を鹿と間違う”とか…。ここから生まれた「馬鹿」という言葉など最たるものだ。この「馬鹿」にまつわる話としては、平成八年におきた我が宗門の大学「仏教大学」で、石畳デザインの空充秋氏が寄贈した門柱騒動がある。大学の正門に彼は「平成之大馬鹿門」と刻んだから大学側は激怒した。空氏は「学んで馬鹿になり、馬鹿になって偉くなる。それが平成之大馬鹿門を通る若者だ」と主張されたのだが、大学側は「見る人すべてには作者の意図はわからない」として、結局門は作者が持ち帰ってしまった。もし門があったら話題になり、入学志望者は増えていたのではないかと残念である。
今月28日に増上寺で私が理事長をしている法然上人鑽仰会が月刊誌『浄土』が創刊1000号になったことを記念して、増上寺法主の小澤憲珠台下と、鎌倉円覚寺派管長の横田南嶺老師と、仏教学者の平岡聡師で鼎談を開催する。そのお招きしている横田南嶺老師の小冊子『「ばか」になる修行』に、横田老師の師匠小池老師がよくおっしゃっていた言葉として「桃栗三年柿八年、柚子は九年で実を結ぶ。梅は酸いとて十三年、みかんの大ばか二十年」を紹介し、「禅の修行は年数がかかる。大ばかになるまで修行しなければならない」と言い、修行を始めた間もないころ、横田さんは小池老師に「ばかになるのが禅の教えならば、何も勉強しなくていいのですか?」と聞いたところ、「何も勉強しないのはただのばかだ。勉強したうえで更にばかになる修行をするのだ」と言われたという話が載っていた。
法句経に「もしも愚者がみずから愚であると考えれば、すなわち賢者である。愚者でありながらみずから賢者と思う者こそ、愚者だと言われる」とある。「ばか」という言葉、これは人に向かって言う言葉ではない。人向かって言えば蔑視語で使ってはいけない言葉である。しかし自分に向かって言う言葉としては大事な言葉になる。わからないことは、勉強しないとどこがわからないかがわからない。学んで初めて自分がわかっていなかったことがわかる。そんなことを学ばせてもらった。
また、この「ばか」という言葉、元々は仏教語のようだ。インドの言葉「マハー」からできた音写語「摩訶」からの言葉で偉大なとか、すぐれたいう意味である。確かに「ばか」は”ばか力”とか、”ばかにうまい”という使い方もしている。「ばか」という言葉もなかなか奥深いと感じられた。
合 掌
2026年1月31日 - ≪今月の言葉≫
針祭る光り初めたる樹々の芽よ 加藤千世子
折れた針を供養する針供養
まだまだ厳しい寒さの中で
黙って耐えてきたものに芽生えがある
枯れ木も生き抜いたことをあらわしている
2026年1月1日 - ≪法話≫
1月のお話
新年明けましておめでとうございます、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
今月は弟子の岱忠が担当させて頂きます。
今年は午年です。午年は、変化を恐れず新しい挑戦に踏み出すパワーを秘めた年とされ、行動力や独立心を促す年と解釈されています。また、十二支の中で丁度真ん中にあたり、時刻では十二時を指し、いわば折り返し地点となり、転換期ともいえるのでしょう。
そして、馬と人との関係を考えると、現代に至っても車の速度や運搬能力の例えに○○馬力というように、私たちの生活には欠かせない存在であることも言えると思います。ですが、馬は時として飛び回り、制動が効かず大変な目に合うこともあります。現代社会でも、AIが幅広く導入されて、世の中はめまぐるしく動き回る年ともいえるのかもしれません。ですが、しっかりと手綱を引くことで新しい時代になるのではないでしょうか。
さて、馬の話となりますと、古代中国の思想をまとめた淮南子の人間訓が由来の「人間万事塞翁が馬」の話を思い出します。
これは、中国北方の塞(とりで)近くに住む老人(塞翁)の飼っていた馬が、遠くの異民族(胡)の地へ逃げてしまいました。近所の人々が慰めると、塞翁は「これは幸福なのかもしれない」と言いました。そして数か月後、逃げた馬が胡の地の優れた馬(駿馬)を何頭も連れて帰り、人々が祝うと、塞翁は「これは不幸かもしれない」と言いました。その後、塞翁の息子がその駿馬に乗って遊んでいると、落馬して脚の骨を折ってしまい、人々が見舞うと、塞翁は「これは幸福なのかもしれない」と言いました。その一年後、隣国との間に戦争が起こり、塞の近くの若者たちは多くが徴兵され戦死しましたが、塞翁の息子は脚を折ったためその兵役を免れ、命拾いしたという話です。
人生において、幸不幸は予測しがたいことであり、私たちに何かが起こるとその都度一喜一憂しがちであるということを戒める話で、もっと言えば、苦があれば後に楽もあり、またその逆もあると捉えることがこの教訓の解釈だとしてしまいます。ですが、これは日本人的な解釈のようです。苦がいつまでも続くことがあった場合そんなことが言えるのでしょうか。
この語をまとめた中国で解釈すると、苦の中に幸が内包しており、また、幸の中にも苦が内包していると解釈することがこの教訓話なのです。ものごとを捉えるときに自身の尺度で勝手に推し量ってしまい、なかなか不幸の中にも幸があるとは言えないこともあるかとは思います。ですが、少しでも見方を変えてみることができれば、それは幸せになれるのではないでしょうか。
悪いことがあれば後に良いことがあると時間の流れで捉えるのではなく、そのものごと一つには良いことも悪いこともあると見方を変えて多面的にみることが仏教的なものごとの見方なのだと思います。
そして、この世に生きていく限り多くの辛いことや悲しいことなどの苦しみがありますが、その苦しみの中でも、分け隔てなく必ずやお救いくださる阿弥陀様が存在するということが如何に幸せなことなのかと私は思います。ものごとを極端に捉えてしまいそうになった時、お念仏をお称えし阿弥陀様に委ねることで心が落ち着くのだと私は思います。
今年は飛翔の年となりますが、今一度、自身を省みて一歩一歩心を穏やかに邁進できるよう努めてまいりたいと思います。
合 掌
2025年12月1日 - ≪今月の言葉≫
仏名会ともし火あふつ起居かな 蝶 夢
仏名会は年末に念仏を唱え懺悔をする会
僧侶は立ったり座ったりの礼拝行を行う
その時ろうそくの炎が風に揺られる
十八日の晩寺では務めます。是非ご一緒に。
2025年12月1日 - ≪法話≫
12月のお話
先月天皇陛下の長女愛子さまがラオスを公式訪問された。その時「パーシー・スクワン」と呼ぶ、白い糸を左手首に巻く儀式が行われた。幸せを祈る儀式で、身体の中の魂が身体から遊離すると不幸になることから、糸で結びつけるために行うものだそうです。結婚、誕生、旅立ちなどいろいろな場面で行われるそうで、私も以前ラオスに行ったときしていただいたような気がしてきました。
私が訪れたのは12月中旬だったのですが、どこにもクリスマスの宣伝がない、「静かなる仏教国」というのが印象でした。
日本では12月に入るともう、どこもかしこもクリスマスになりますが、仏教でも12月は大事な月で、お釈迦様がお悟りを開かれた記念すべき時、成道会を迎えます。この成道会(お悟りの日)は12月8日で、この日お釈迦様はブッダガヤのピッパラ樹(のちの菩提樹)の下で、明けの明星が輝くときお悟りを開かれたといわれています。
ここまでお釈迦様は王子の生活を捨て、苦行を繰り返し、中でも断食の苦行は、周りの誰もがこの人は死んだと思われたほどだったと言われています。しかし農夫の「琵琶の糸、きりりと締めればぶつりときれ、さりとてゆるめりゃべろんべろん」という歌に目を覚まし、中道を選ぶことを決め、真理に目覚めたと言われています。ここでいう中道とは真ん中ということではなく、その人にとってちょうどいいところ、いい加減なところをさします。この「いい加減」もアクセントで二つの意味があります、ひとつは適当にやること、もう一つは風呂の湯加減などのいい加減です。以前はお釈迦様の「いい加減」は、断然後者、風呂の湯加減の方だと思っていましたが、最近はどちらでもいいのかななどと思っています。お釈迦様の教えは決めつけることを避けているように思えます。龍樹の言葉「日照りの時の雨は善であり、洪水の時の雨が悪である」にもあるように、善悪も受け取る人、状況によって替わることを言います。真理がその人、その時、その場所で変わるのです。怠けている人に厳しく、一所懸命な人にはやさしくする教えが仏教だと思っています。
12月はとかく忙しい月です。忙しいとついつい人にも厳しくなりますが、そんな時こそ和顔愛語、笑顔に努めましょう。
アメリカの哲学者ウィリアム・ジェームズも言っています「人は幸せだから笑うのではない、笑うから幸せなのだ」と、笑顔は単なる感情の結果ではなく、心を動かし、状況を変える力を持っている言われています。たとえ無理に笑ったとしても、その表情の変化が心に小さな明かりを灯す。やがてその心の明かりが周りの人の心も温めてゆく。「笑う」ということも最初の1歩なのです。その笑顔が次の笑顔を連れてくるのです。
合 掌
2025年11月5日 - ≪今月の言葉≫
人々を しぐれ宿は 寒くとも 松尾芭蕉
冬を感じさせる寒い中で句会の友の前で詠まれました。
寒さすらも楽しむという強い思いがこめられた句なのでしょう。
たとえ寒くても分かち合える友がいればその風情も楽しめる。
僕にはそのように詠まれている様に思います。